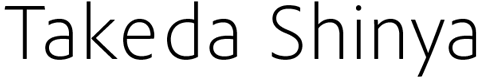誕生日は旅先で迎えると決めている。そう自分に課せば、少しでも見聞を広められるかもしれない。そう思ったからだ。
昨夏はパリで一つ歳を重ねた。新型コロナウイルスの影響がまだ色濃く残る中での珍道中。すでに記した通り、なかなかできない体験をさせてもらった。
2017年の誕生日の前後はロンドンにいた。古希を過ぎた現在まで、さまざまな国を訪れた。その中でも「いい国だ」と心から思えるのは英国である。私の感覚に最も添うものを感じる。
若い頃は彼の国にあまりいい印象がなかった。パリに足を向けるついでに立ち寄る程度にとどめていた。
毛嫌いする理由は簡単。欧州に出かける際の前評判で「英国の食べ物はひどくまずい」と聞いていたからだ。
2020年1月31日、英国は欧州連合(EU)を離脱した。それ以前のEU加盟時代、シティ・オブ・ロンドンにフランス人が多く移入している。英国首都の食文化は豊かになった。各地の民族料理も楽しめる。かつて七年戦争後には「太陽の沈まぬ国」と謳われた大英帝国の中心である。街を歩けば、いろいろな髪、目、肌の色を目にする。昨今流行の多様性重視の傾向は英国の食文化を確実に向上させたのだ。
農林水産省が公表している世界各国の食料自給率(カロリーベース)の統計がある。英国の場合、1960年代までは4割程度を推移していた。現在は7割を超えている。第二次世界大戦後、一貫して上昇を続けている点は注目に値するだろう。
考えてみれば、もっともなことだ。英国はグレートブリテン島と北部アイルランドから成る島国。大陸から他国の軍隊が侵攻してくることも少ないが、有事の際には食料をはじめ必要な物資が滞る危険性も秘めている。第二次大戦で英国政府と国民はつくづく身にしみたのだろう。戦後、工業化に邁進する一方で通奏低音のように食料自給率の向上にも注力していった。その結果、今がある。
ここで、わが身を振り返ってみたい。大陸の端にある島国にして先進工業国。日本と英国はどこか似通っている。かつては同盟を組んでいた。英国の理念や政策には日本が参考にすべき点が少なくない。第二次大戦では日本も同じような経験をしている。やはり食料が入ってこなくなった。島国として災禍の恐れを免れやすい。だが、供給路を断たれると、たちまち窮乏するしかない。島国の現実を英国と同じように身にしみて感じた。
食料自給率に目を転じてみる。第二次大戦が火蓋を切る直前、日本は6割ほどを維持していた。敗戦後、長きにわたる低落が始まる。現在では40%を割り込んでいる。戦後、4割から身を起こし、7割まで引き上げた英国とは対照的だ。農水省は1974年、全穀物(米、とうもろこし、小麦、大麦など)の「安全在庫水準」を17~18%と定めた。当時の統計ではこれをはるかに上回っている。だが、2017年にはついに割り込んでしまった。安全な水準に満たないとは、つまり現在も危険な状態にあるのだろうか。言うまでもないことだが、食料供給の確保は安全保障の重要な柱の一つだ。国防という国家の要において英国とは正反対の方向に国を挙げてひた走っている。それが現在の日本の姿である。穀物の在庫にすら事欠く先進国とは何か。どう考えても、地道に食料自給力を蓄えていった英国の路線が正しいのではないのか。
2017年の渡英で味をしめた私は翌年の誕生日直前にもロンドンの地を踏んだ。1年ぶりにシティを徘徊する。
「どこか安い部屋を買えないものか」そんなことを思い立ち、いろいろと物件を渉猟してみた。すぐにわかった。英国の不動産価格は当時、全体に上げ潮にあったのだ。2012年のロンドン五輪。大会誘致が決まったあと、「閉幕後には大不況が襲う」といった無責任な予想も聞こえた。あにはからんや、英国経済はむしろ持ち直している。
私のロンドン観光のコースはいわば「おのぼりさん」そのもの。もともと教会や聖地が好きでもあり、もっぱらそうした史跡を辿った。英国国教会の歴史を遡ると、ヘンリー8世の行状に行き当たる。テューダー朝第2代のこの王は実に6度の結婚を繰り返した。
中世後期以降、欧州各国では王権と教皇権のいさかいが顕著になっていく。それでもイングランドの教会はローマとの一致を維持し続けていた。両者の間に決定的な分裂を生んだ原因はヘンリー8世によるものだ。よく知られる離婚問題のこじれである。キャサリン・オブ・アラゴンに三下り半を突きつけようとした英国王に対し、教皇クレメンス7世は婚姻無効の宣言を却下。キャサリンの甥は神聖ローマ帝国皇帝・カール5世であり、問題は単なる離婚の可否を超え、複雑な政治色を帯びていく。紆余曲折の末、ヘンリー8世はアン・ブーリンと再婚し、教皇に破門される。国王は国王至上法(首長令)を公布し、イングランド教会の首座に君臨した。ヘンリー8世はカソリックの教義で離婚できないことを不服とし、政治的な解決を図り、ローマ教皇と決別したのだ。この国王は英国庶民から絶大な支持を得てもいる。
英国国教会の成立に関してはマーケッターの立場から私にも見解がある。一言で言えば、背後に金目の匂いを感じるのだ。ヘンリー8世は英国の聖職者たちを王権に従わせ、教会が持っていた資産を全てわがものとした。当時の欧州で最も富裕だった階層といえば、聖職者だ。15世紀から16世紀にかけて活躍した神学者デジデリウス・エラスムスはカソリック寺院にいかに富が集中しているかを書き残している。寄進されている品々がいかに価値があるものばかりか。碩学は強調してやまない。
マーケティングの視点からもう一つ指摘しておきたい。カソリックの歴史を振り返ると、司祭が殺められる悲劇がしばしば起きてきた。だが、ローマ教皇庁もなかなかに商魂たくましい。殺害現場を「聖地」に置き換え、ビジネスに結びつけてきた。例えば、司祭が殺された場所を聖地とする。そこに近づくと、病が治る。そんなストーリーを喧伝し、巡礼者を集めるのだ。惨禍の場を信者が救いを得られる地へと意匠替えしてはばからない。教会の歴史を調べてみると、結構血なまぐさい側面もあることに気づかされる。
英国国教会の成立に話を戻す。ローマ教皇との決別でヘンリー8世は教会の富を一手にした。当時の英国はせいぜい二流半程度の格付けに甘んじているに過ぎない。覇権国・スペインに対抗するには軍備増強が必須の課題。国力をかさ上げする原資として教会の富は垂涎の的だった。私に宗教の素養があるわけではない。気まぐれから英国滞在中に日曜日のミサをのぞいてみた。隣にいた妻に尋ねた。ちなみに彼女はカソリックの学校育ちである。「四谷駅前の聖イグナチオ教会と同じじゃないか?」「当たり前じゃないの」ごく簡素な回答だった。英国国教会はプロテスタントに分類されることもある。高校の世界史でも確かそう教わった。だが、同教会は他のプロテスタント諸派とは少々違う。前述した通り、分派した理由は教義上の問題ではない。あくまで政治的問題(ヘンリー8世の離婚問題)が原因。分裂に当たっても、カソリック教会の教義自体は否定していない。従って典礼の上ではカソリックとの重なる点が非常に多い。ヘンリー8世が典礼をどう見ていたのかはわからない。変更するための能力がなかったのか、「そのままでいい」と思ったのか。手は加えなかった。英国国教会の誕生で変わったのは、富が王室に移行した点だけだ。
NHKは2022年に大河ドラマ「鎌倉殿の13人」を放映。23年の大河は「どうする家康」だった。主人公はそれぞれ北条義時、徳川家康。武家政治史上有数の智謀に長けた権力者である。家臣団を従わせるのに主君の側には富が必要。この点は洋の東西を問わない。英国でも騎士団が忠誠を誓うのは王に財があるからだ。ヘンリー8世には当初それがなかった。協会から召し上げた財産を地域に分配し、ようやく臣下が指揮に従い始める。統治能力は格段に高まった。ヘンリー8世は英国を一等国に押し上げるため、世間体にも異常にこだわった。衣装に巨額を投じたことでも知られる。鹿鳴館時代の日本を想起させる挿話だ。二流半が一流に伍していくためにはそれなりのもとでがいる。国王は教会の富を活用し、国の基礎を築いていった。
ヘンリー8世とアン・ブーリンの間に生まれた娘が後のエリザベス1世である。先般逝去したエリザベス2世とは遠縁に当たるものの、直接の血縁関係はない。エリザベス1世は英国の絶頂期を象徴する存在であり、在位期間は「エリザベス朝」としばしば称される。当時の覇権国スペインの無敵艦隊を迎え撃ったアルマダ海戦で知られる。エリザベス1世は王室所属の34隻に加え、寄せ集めの武装商船163隻を差配。その大半は海賊船だった。無敵艦隊はアイルランドの北側海域にさしかかったところで暴風雨に遭遇。不慣れな海域で制御を失った艦艇は次々と座礁したり沈没しりした。スペイン側の船は30%以上が沈没。兵士の約半数が落命したといわれている。スペイン側の犠牲は戦闘によるものではない。多くは嵐に起因している。だが、当時は圧倒的に優勢と見られていた無敵艦隊がなすすべもなくその多くの艦艇を失ったのは事実だ。結果的にこの海戦はスペインの没落の第一歩となった。一方で英国は海洋国家として覇権に足掛かりを得ていく。その後、英国は文字通り世界中に版図を広げ、今日につながる素晴らしい国を作った。
2022年の国際政治を象徴する出来事、ウクライナ侵攻。その背景には武器や資源を売りたい米国の思惑があった。英国の視座から検討すると、戦争の異なる横顔が見えてくる。ドイツがEUで台頭を続けることへの警戒感には根強いものがある。現在、建設中のフェーマルン・ベルトトンネルも英国にとっては目の上のたんこぶだ。ロラン島(デンマーク)とフェーマルン島(ドイツ)の間を結ぶこの沈埋トンネルが完成すれば、ドイツからスウェーデンやノルウェーへのより容易で迅速な移動が可能になる。そうなれば、欧州圏内の勢力均衡は破られるのが必至だ。
懸念事項はそれだけではない。欧州大陸にロシアからのパイプラインが普及していけば、英国の地位は明らかに低下する。英国政府としては看過できない事態だ。何とかする必要があった。
これらの憂慮すべき事態(あくまでも英国から見れば、だが)がロシアのウクライナ侵攻の結果、一挙に雲散霧消した。これは現実である。欧州全域は厳しい冬を迎えている。報道によれば、折からのエネルギー供給不足も相まって多くの人が凍死しかねない状況だという。こうした環境下で英国のEU離脱の背景をもう一度噛み締める必要がありそうだ。ドイツの「富国強兵」は英国にとって悪夢でしかない。第一次世界大戦後、賠償金の支払いで塗炭の苦しみにあえいでいたドイツに救いの手を差し伸べたのはソ連である。ドイツに原油を提供し、見返りに技術の供給を受けた。この構図はウクライナ侵攻前の両国間にも重なる。ロシア革命後、国力を増大させなければならないソ連にとってドイツの技術力は喉から手が出るほど欲しいものだった。莫大な対外債務で最貧国に落ちぶれていたにもかかわらず、ヒトラーが率いるナチスが強大な軍備を用意できたのはソ連の援助があればこそだった。独露が結託する理由はある。ロマノフ朝の帝政をドイツ人の官吏が支えていたのは歴史的な事実だ。ロシアからドイツへのパイプラインの拡大が実現すれば、ドイツは欧州の盟主として大きな権力を握る。英国としては手段を選ばず阻む必要があった。これは歴史の必然である。
ロシア国防省のコナシェンコフ報道官は2022年10月29日、聞き捨てならない発表を行った。ロシア産天然ガスをバルト海経由でドイツに送る海底パイプライン「ノルドストリーム」と「ノルドストリーム2」で9月末に起きた爆発とガス漏れ。これらが「ウクライナ軍を支援する英軍関係者が計画と実行に関与したテロ行為だ」と明言したのだ。
日本の報道が偏向しているのは今に始まったことではない。映画『007』を想起させる事件が国内で詳報されることはなかった。何ら不思議な点はない。諜報は英国のお家芸だからだ。
食糧供給に関する彼我の隔たりについてはすでに述べた。英国のしたたかさ、ドイツの脅威への分析と対処に何を学ぶべきだろうか。「平和のための勢力均衡策」と彼らは言ってはばからないだろう。本質や根本を見極める必要がありそうだ。
2022年末、倉庫を片付けていると、懐かしい本が出てきた。バートランド・ラッセル著『西欧の知恵』。高校生の頃、買い求めたものだろう。ラッセルの名言には有名なものがあまたある。中でも今、注目したいのはこれだ。
「道徳は常に変化している」
これこそが西洋の知恵の真髄ではないか。近代日本もラッセルの言に学んでおく必要があった。第二次大戦の講和においてスターリンに仲裁を頼んだり、今また日米安全保障条約を「曲解」して「いざというときは米国が助けてくれる」と思い込んだりする。いずれも道徳の変化を知らない、または気づけない者の妄言に過ぎない。今、日本のマスメディアを賑わせているのは米国民主党寄りの情報だけだ。この国がどこまで独自の情報をつかみ、意思決定に役立てているか。誠に心許ない。
列強の思惑にさんざん振り回されてきたインド政府は今、どう振る舞っているか。少なくとも彼の国には独立自尊の気概が見て取れる。
年末にエリザベス女王を回顧する映像がテレビで流れていた。変化への対応が十分にできた君主だったとあらためて思う。かつて植民地として統治していた国の大統領と彼女はダンスに興じていた。道徳は変化する。ならば、受け入れるしかない。政治の根源を見た気がした。
一方でこんな言葉を吐いた経営者もいる。
「道徳というものは、時代とともに変わるようなものではない」
言葉の主は出光助左。石油元売会社出光興産の創業者である。出光の言わんとするところはわかる。心酔もするが、これはあくまで精神の話だ。原理原則や金科玉条は確かに大事だが、道徳はそれらとは本質的に異なる。
世界の中で行動するには英国の知恵をあらためて取り入れる必要がありそうだ。ひとまず、国権の最高機関・国会が機能しているさまを見てみたい。英国議会は本当の意味で機能している。あるいは日本の国会は機能しないように作られているのかもしれない。渡英の際、議会を見学したことがある。議事堂の椅子にも座ってみた。討論が可能な構造になっているとすぐにわかる。どこかの国の議会が「シャンシャン」のために設計されているのとは大違いだ。
国家がここ一番で一流に生まれ変わるためには宗旨替えも平気でやってみせねばならない。ある意味での野蛮さも必要だ。カソリックが英知に富んだ狐だとすれば、英国はしばしばライオンに例えられてきた。
日本の未来像はどんなものなのか。議論はすでに出尽くしているのか、まだ始まってもいないのか。偏見や感情はひとまず脇に置いて、虚心に英国を見つめることから始めたい。
Photo ©mira66 2015. Licenced under the CC BY 2.0.