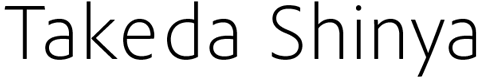今から32年前、1990年は東西ドイツが再統一を遂げた年に当たる。
10月1日はドイツ統一の日と定められている。
1989年11月にはベルリンの壁が崩壊。91年にはソビエト社会主義共和国連邦が内部分裂から単独国家としての存続を終了した。
「東側」と呼ばれた社会主義国家群が歴史的な役割を終え、冷戦は終結に向かった。
日本でいえば、1989年に裕仁天皇が逝去。昭和天皇と追号された。明仁天皇が即位し、平成の御世が始まる。
31年で幕を閉じた平成年間は冷戦終結後の歴史とほぼ重なる。
経済でいえば、1991年3月のバブル崩壊以降の「失われた30年」と同義と言っていいだろう。
言うまでもないことだが、第二次世界大戦でドイツは日本と同じ枢軸国側に立って戦った。
冷戦構造下で東西に分断されていたドイツの再統一が日本に影響を及ぼさないわけがない。
1990年10月3日は冷戦終結後に唯一の覇権国家として君臨した米国と日本の関係にとっても画期となった。
もちろん、日本が米国に隷属している点では変わりはない。主権国家としては誠に中途半端な「保護領」であり続けている。
変わったのは次のような事柄である。
東西冷戦下で我が国は「宗主国」である米国にお目こぼしをいただいていた面がある。
主に経済の分野においてだ。
米国の社会学者アズラ・ヴォーゲルが『ジャパン・アズ・ナンバーワン』を著したのが1979年。
この書名は日本経済の黄金期とも呼ばれる1980年代の代名詞としてしばしば用いられてきた。
戦勝国であり、西側の盟主でもある米国にとって、日本が「ナンバーワン」の座に上り詰める事態は決して愉快なものではなかっただろう。
だが、冷戦という特異な国際情勢によって、それは許容されていた。
当時の米国にとって第一義は冷戦下で社会主義圏に対し優勢を保ち、西側諸国を統括することだ。
西側の覇権を守るためには、日本から経済的に圧迫される程度のことには目をつぶらざるを得なかった。
先述の通り、1990年前後にベルリンの壁が崩壊し、ソ連が解体していく。
米国は冷戦の勝利者となった。
東西対立が幕を下ろすとともに、日本はお役御免となった。
それまではお目こぼしをいただいていた経済発展も米国から冷静な目で検討される。
日本は単なる競争相手となった。
米国にとって日本は保護領、属州に過ぎない。
そこまで被害妄想的に捉えなくても、かの国は競争においてどこかあっけらかんとしたところがある。
まるでアメリカンフットボールの試合に臨むかのように、競争相手となった国を叩きにいく。
冷戦終結後、当たり前のこととして米国は日本に普通の経済戦争を仕掛けた。
驚いたのは日本の政府や財界である。「まさか」と思ったものの、宗主国はどうやら本気だった。
1990年前後を境に日本は戦いに敗れ続けた。30年の長きにわたって米国のカモにされ続けたのだ。
両国の経済戦争は米国の一方的な勝利に終わった。米国の覇権構想は日本に対して完成する。
「失われた30年」とは、そういう時代だった。
私がそんなことをつらつら思ったのには理由がある。
国内を騒がせている円安について考えを巡らせていたからだ。
おそらくこの傾向は当分続くのだろう。
今回の円安は「悪い円安」だといわれる。
経済の門外漢である私には判然としない。
ただ、通貨安は国内総生産(GDP)にとってはプラスの要因には違いない。
通貨安は輸出主導の国内優良企業には有利に働く。輸入主導の平均的な企業には不利。全体としてはプラスになる。
従って、輸出依存度などに関わらず、どんな国でも自国通貨安はGDPプラス要因になるわけだ。
国際機関での経済分析もこのことを裏付けている。
経済協力開発機構(OECD)の経済モデルによれば、10%の円安だと、1~3年以内にGDPは0.4~1.2%増加する。
早ければ、来年度の数値にも反映されるかもしれない。
日本経済はほっと一息つくことになるのだろう。
もちろん、これは国内企業が力を尽くした結果とはいえない。
またしても他力本願の賜物だ。
円安基調にもかかわらずゼロコロナ政策による出入国制限が続く限り、これまで日本に金を落としてきた中国人観光客は戻らない。
これは妥当な予測だろう。
だが、中国共産党は今秋、路線転換を図った。お家芸だった集団指導体制を捨て、習近平の永世皇帝への即位が既成事実化しようとしている。
ことによると、この新体制は日本の思惑とは関係なく、経済に影響をもたらすかもしれない。
米国と覇権を競っている中国が日本に対する「餌」として出口を緩める可能性があるからだ。
米中覇権戦争の傍ら、親中派へ働き掛けが水面下で行われる。甘い囁きに彼らは乗るのだろう。
多くの中国人観光客がまた国内に押し寄せ、外貨がじゃぶじゃぶと入ってくる。
日本はまたも我が世の春を謳歌するのだ。
岸田文雄首相にしてみれば、漁夫の利そのものだ。誠に強運の持ち主としか言いようがない。
国際社会の動向には何ら不思議な点はない。全くあからさまと言っていい。地政学に基づいて動いている。
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が読み違えたのか、嵌められたのかは定かではない。
だが、目下のウクライナ侵攻でロシアは大消耗戦を強いられている。米国の利益は莫大なものになるだろう。
米国の一強体制に陰りが見え始め、覇権争いは米中露の三国を軸に進んでいくとの見方もあった。
だが、ロシアの脱落は明らかだろう。ウクライナという傷口は今後しばらくはプーチンとロシアを責め苛むに違いない。
「失われた30年」、ポスト冷戦時代とほぼ同義である平成年間が終わった。
今、日本は今後をどう見通すべきなのだろうか。
そのためには、まず、足元の状況を見つめなければならない。
この30年で私たちはどんな国を形作ってきたのか。なるべく冷徹に実態を観察することだ。
冷戦下の日本はどんな姿をしていたのだろう。今一度、思い返す作業にも意味がある。
米国が快くは思っていなかったであろう往時の日本とはどんな国だったのか。
「護送船団方式」が当たり前に通用していた時代が懐かしい。
優秀な官僚が中央省庁で政策を立案し、企業を差配していた。
米国との経済戦争では連戦連勝である。
今では信じ難いことだが、当時は日本的な労働・雇用慣習を米国が褒めちぎっていた。
年功序列や企業内組合、終身雇用はその一端である。
そうした風潮がこの間まであったことを皆すっかり忘れている。
80年代の日本はなぜ「ナンバーワン」だったのか。
その根拠は日本的な働き方と官庁・官僚の優秀さに求められる。
米国は日本の強みを徹底的に研究し尽くした。
そして、30年の歳月をかけて徹底的に潰してみせたのだ。お見事というほかない。
霞が関の住人たちの心性も今や変わり果てた。
公益には目もくれず、省益だけを追い求める。そんな役人ばかりだ。
彼らを「省役人」と私は呼んでいる。
官僚は本質的に「サブ」である。悪くいえば、参謀根性の持ち主。
大義名分を与えられないと、動けない。王様に仕える存在であり、仕える技術を磨いている。
米国が親分にうまくすり替わったことで、省庁も変化を余儀なくされた。
大義名分や仕えるべき存在がなければ、役人はいとも簡単に近視眼的な思考様式に染まっていく。
省益至上主義に陥りやすい体質はもともと備わっている。
官僚は今、大義を求めている。
中国やロシアの人民が「皇帝」を欲しているようなものだ。
一方の国民も変貌した。
もともとこの国の人々は熱しやすいところがある。助長したのはメディアだ。
かつてアジア太平洋戦争へと突入したのも、軍部だけの責任とばかりはいえない。
旧憲法下にも民主主義はあった。国民の熱狂的な支持があったからこそ、軍部の独走が可能になったのだ。
戦前の朝日新聞を見てみれば、それは明らかだろう。
冷戦終結から30年を経て、日本国民はすっかり不寛容になってしまった。
非難することでアイデンティティーを維持しているかのようだ。
「非難国民」の誕生である。
非難の矛先はしばしば政府に向かう。その政府がまたいただけない。
ある意味で無能な政府になり下がっている。何らビジョンが示せない。「無能政府」と名付けて差し支えあるまい。
米国との経済戦争で完膚なきまでに敗れたのは事実だ。無能の謗りは免れない。
小泉純一郎内閣以降は政府の劣化が特に顕著だ。
人気取りのような小手先の劇場政治にかまけ、米国に完全にしてやられている。
そんな小泉首相を国民は支持した。実に浅薄としか言いようがない。
その後は政権発足時は支持率が上がり、失敗すると非難する傾向が定着した。
怨嗟の表れだろうか。「神輿は軽くてパーがいい」を地で行くようなものだ。
国民は非難するだけ。「無能政府」は非難を避けるだけ。そんな不毛な状態が長く続いている。
いうまでもないことだが、中央省庁は本来、内閣を支えなければならない。
選挙で選ばれた国会議員で構成される内閣が大方針を示し、官庁がそれを実現すべく法制度に落とし込んでいく。
省役人、非難国民、無能政府。
この三者で構成されているのが目下の日本である。これこそ最も支配しやすい保護領の形ではないだろうか。
最近、米国では「地経学」が注目を浴びている。経済や資源の時間的、空間的、政治的側面の研究をする学問だという。
確かに地経学の概念は新しい。だが、よくよく見てみると、これはつまり、マーケティングが世界を支配することに他ならない。
文明とは何か。きれいな言葉を用いれば、いくらでも言い繕える。
だが、その本質は国家が他国を尻目に自分の側に富が流れてくるよ王にお椀を傾けるよう仕向けることだ。
ロシアはその点、洗練された文明国とは呼べない。
この30年間、日本は米国にとって都合のいい形に甘んじてきた。
その間に米国主導でなされたことは何か。
それを踏まえた上で日本もプレイヤーとして正確にゲームを戦っていく必要があるだろう。
目的意識を持たなければならない。
国際社会においては覇権戦争に勝たない限り、生き残りは難しい。
表現が正しいかどうかわからないが、地球上の国家はいずれも限られた資源を奪い合っている。
つまり、地政学的な原理で動いているわけだ。
米国が地経学を唱え始めた以上、マーケティング優位な情勢はまだまだ続くだろう。
あからさまな国際社会であからさまな正義がこの30年間、幅を利かせてきた。
その結果、日本経済は世界GDPの中で占める地位を確実に低下させてきている。
何度も言うが、これは敗戦である。大きな器を自国の都合のいいように傾けて飲む。
そのために私たちは何をしてきたか。相手国は何を押し付けてきたのか。
それをはっきり見定めた上で対処していかなければならない。
今般の円安を私は天佑と捉えている。
これをテコとして、日本がもう一度地経学で勝っていく体勢を整えなければならない。
この30年間のありようを全面否定するには及ばない。
国家が発展するとき、官庁と企業の関係はどうあればいいのか。
米国がもっともらしく言い募る「スタンダード」を安直に信用してはいけない。
宗主国が躍起になって潰したものは何だったのか。
それを見定め、再評価して、もう一度使えるようにすればいい。
ここまであからさまな情勢について、日本のマスメディアは決して触れようとはしない。
そこまでいい子になる必要があるだろうか。ちょっとぶりっこが過ぎやしないか。
演じているつもりが、いつの間にか本当になってしまう。人間にはそうした習性がある。
省役人と非難国民、無能政府。
これらを三位一体で演じてみせているのなら、まだいい。
だが、いつの間にかそれが身に染みているようでは取り返しがつかない。
Photo ©Jovel 2010. Licenced under the CC BY 3.0.