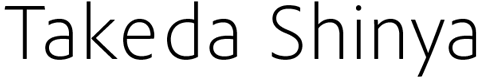前回も触れた台湾の友人たちとの付き合いから話を始める。昨年夏のことだ。台湾の友人たちと交歓する機会を設けた。もっともお互い自由に行き来できる状況ではまだない。オンライン上、リモートでのことだ。
しばらく連絡を取り合っていなかった。挨拶を交わし、近況を知らせ合う。
たまたま話題が家族に及んだ。何の気なしにこんなことを口走った。
「娘がシカゴに住んでいましてね。亭主が現地で仕事をしているもので。孫は向こうの小学校に通っています。おかげさまでサッカーに空手にと、楽しくやっているらしい。そのうち、米国人になっちゃうんじゃないかな」「ああ、そうですか」で終わる話だとばかり思っていた。だが、友人たちの反応は想定したものと少しばかり違っていた。
「さすがだ」という声が飛び交う。称賛の嵐だった。彼らの言い分はこうだ。
「竹田さんはシェルターを米国にすでに確保しておられる」
確かに娘一家はそれなりに大きな邸宅に住んでいる。そんなことに触れると、途端に「シェルターの準備ですね」と感心されてしまうのだ。
彼らは何を言っているのだろう。当初は判じかねた。何度説明しても、「ご謙遜を」と返ってくる。
しばらく会話を続けるうちにようやく輪郭が見えてきた。彼らは一様に将来への不安を抱き、対策を講じているのだ。
彼らの中にも米国につてのある者はいる。海外での支店長経験を持つ銀行OBもその一人。現頭取とも親しく口がきける彼は母親をカリフォルニアに住まわせている。
だが、それはあくまで名目上のことだ。台湾海峡周辺の雲行きが怪しくなれば、いつでも退避できるような家を米国に確保する。それが本来の目的だという。
彼らの現状を知れば、娘の話への反応も納得がいく。台湾同様、日本の近未来にも暗雲が垂れ込めている。友人たちはそう察しているのだ。
とはいえ、私は「まさか」とたかをくくっていた。
国際的な常識に照らしてみれば、恐らく私の読みは楽観的すぎる。台湾の友人たちのほうがはるかにまともだ。統制されきった日本の情報に慣らされている身には何も見えていない。
当の娘自身にしても同じようなものだ。子供の教育を考えると、帰国したい。そんな悩みを抱えているのが実情であり、故国の危機は念頭にない。
平和な日本で暮らすこと。いつしか私の心は一つの現実離れした思い込みによって支えられるようになっていた。
台湾海峡で2026年に何かが起こるとの観測は現実になされている。前回のコラムで指摘した通りだ。台湾の人々にとって、それがどれほど過酷なことか。
我が身に置き換えてみれば、すぐにわかる。私が現在日本に保持している財産を全て処分しなければならなくなったとする。その上で海外で暮らしていかなければならない。本当に大変なことだ。「そんなことはあり得ない」と心のどこかで決めつけようとさえしている。
そう思える自分がいかに平和ボケしているか。台湾の友人たちとの語らいは期せずして現実を突きつけられる機会となった。
平和に対する私の思い込みは現実とは異なる基盤に立脚しているようだ。ことによると、戦後教育を受けた私にとって現行憲法は心の安寧を保つ支えとなっていたのかもしれない。
閑話休題。マーケティングと政策の立案や遂行には少なからぬ関係がある。整合性が取れると思われる政治判断には背景に必ず地政学がある。
地政学とは地理的な環境が国家に与える政治的、軍事的、経済的な影響を大所高所からの視点で研究する学問。マーケティングの発想とも重なる面が多い。
歴史は繰り返すという。人類がこれまでに何度も繰り返してきた愚行や善行。地政学を適正に用いれば、これらを精緻に分析できる。マーケティングの世界では「戦略」や「戦術」といった用語が普通に用いられる。この事実からも明らかなようにマーケティングは第二次世界大戦の戦況を踏まえ、米国で発展した。
例えば、ランチェスター理論。英国のフレデリック・W・ランチェスターが航空機による空中戦の損害状況を研究し始めたことから生まれた。
第二次世界大戦中、当初は日本軍の零戦が米国の戦闘機より優位に立っていた。米軍は故障して島に落ちていた零戦の機体を解体して徹底的に研究。軽い機体と優れたエンジン、パイロットの操縦技術の卓越さを知った。
米国の司令官は零戦に対抗する新型の戦闘機を作るよう命令を下す。並みの発想であれば、零戦より速く飛び、小回りが利く、軽さを追及した機体を目指すだろう。だが、米国の技術者は頑丈で重い機体を開発。巨大なエンジンが2つもつけられ、反転操縦もままならない。この新鋭機グラマンに加え、飛行高度がわかる最新式のレーダーを駆使。米軍は日本軍を追い詰めていく。
その際の戦術は以下の通りだ。零戦の攻撃をレーダーでキャッチし次第、上空にグラマンを3機1組で待機させて迎え撃つ。零戦が飛んできたら、はるか上空から1機目のグラマンが突進。機銃を打ちながら敵機を狙う。1機目が外しても、2機目、3機目が追撃する。
もともと零戦が得意としていたドッグファイト(戦闘機同士による1対1の戦い)を米軍は禁じていた。
しかも、グラマンは零戦の2倍のスピードで飛んだ。あまりの逃げ足の速さに零戦は追撃さえかなわない。一方的に撃ち落されていった。
グラマンの頑丈な機体はパイロットの命を守る上で大きな効果を上げる。次々と優秀な操縦士を失っていく日本軍とは対照的である。
ランチェスターは研究過程で大きな発見をした。出撃する戦闘機の量と質から敵軍に与えられる損害を割り出せる。そのことに気づいたのだ。
それまでの軍事戦略は精神論や哲学、宗教観に支配されていた部分が大きかった。ランチェスターは古典的な観念から戦略を解き放ち、数学的・科学的なアプローチで理論化した。
数学や統計学で戦争を解明する試みは世界初。第二次世界大戦になると、英軍はランチェスターの理論をさらに掘り進めていく。コロンビア大学の協力を得ながら、戦闘機をやみくもに出撃させても戦果を得られないと結論づけた。
戦闘機の数と質を踏まえ、最前線へ飛ばして直接的な戦闘に当たらせたり、敵の後方支援を攻撃して戦闘継続を困難にさせたりと、それぞれの部隊に適した役割を与える。そうしたことが重要であるとの考えに達した。
このように強みと弱みを分析し、傾向と対策を確立する。あくまで理論的に進めていく。
日本は縄文期には長い平和の時代を経験。聖徳太子の十七条憲法は一条に「和を以て貴し」と記している。私が生まれてこの方、国内が戦場になったためしはない。
歴史は地政学の理論通りに動いている。これは事実だ。
2022年2月24日、到底信じられない事態が起きた。ロシアによるウクライナ侵攻である。間もなく1年が経過しようとしている。
だが、これすらも地政学の矩を超えてはいない。専門家の中には「それ見たことか」と感じた人もいたのだろうか。
日本国憲法は前文で次のように謳っている。〈日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する〉
だが、この崇高な理念は絵空事に過ぎない。それを証明して見せたのがウクライナ侵攻である。
地政学の必然に従い、北大西洋条約機構(NATO)は30年近く東方拡大を続けてきた。ロシアのプーチン大統領はこれを打ち戻すべく対処しているに過ぎない。地政学的に見れば、彼の判断もまた極めて妥当といえる。英米を中心とする西側のメディアはプーチンの行状をそろって非難した。こうした振る舞いも地政学が示すあるべき姿をきれいになぞっている。
日本も地政学の枠内で演じられる国際社会のパワーゲームの中で平和を享受してきた。覇権を志向する国々は領土拡大を意図し、摩擦を生じさせる。
引けば押す、押せば引くで均衡が保たれている。この現実は認めざるを得ない。
日本国憲法は第二次大戦直後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)による間接統治の最中という特殊な状況下で制定された。前文はもとより、条文が示す理念は極めて理想主義的だ。一つの教義だといってもいいだろう。起草を米国が主導しただけのことはある。何しろ、禁酒法を施行した過去を持つ国だ。
戦後の日本は憲法の理想主義を盾に経済発展を押し進めてきた。米国から軍事的な貢献を求められても、「押しつけられた憲法があるので、できかねます」とのらりくらりかわす。冷戦構造というこれも特殊な状況下では、それで済んでいた。
朝鮮戦争勃発後、米国に再軍備を求めらた吉田茂首相は「日本の経済自立を不能にする」と当初は拒否した。できるだけ軍備には金を使わず、経済復興。これが吉田に始まる戦後の対米追従政治家たちの基本姿勢だ。
「保守本流」の末裔を自称する岸田文雄首相に至るまで、この流れは変わっていない。
マーケティングの理論に当てはめれば、「軽武装・経済成長」の原則は決して間違ってはいない。だが、戦後はすでに遠くなり、冷戦終結から30年以上が経過した。米国の対日戦略も様変わりしている。バイデン政権は安全保障政策の転換と軍事費の増額を無理強いしてきた。岸田内閣は増税までして応える構えだ。
歴史は繰り返される。戦後日本の外交や安全保障を規定してきた憲法の「教義」を信じたふりをしながら、どこまでやっていけるのだろうか。
地政学の根底には人間が持つ心性の変わらない部分がある。猿の研究者はよく知っているだろう。猿山で観察される力学は極めて地政学的だという。人間は今もって猿的な行動から脱し切れていないのだろうか。
理性よりも感情が先に立つ。これこそが猿山の実態だろう。いろいろと飾り立ててプーチンは説明しようとする。だが、現実には猿山の一方のボスである欧米諸国が約束を違えて東方に勢力を拡大。プーチンは大統領として打つべき手を打っただけだ。これも猿山の論理である。
日本もまた信仰心の現れとして平和憲法を護持すべきなのかもしれない。だが、憲法が指し示す「教義」は今も変わらず健全といえるか。「非核三原則」にしがみつくことで、どれほど確かな抑止力が得られるのだろう。日本がしかるべき報復能力を欲するのであれば、例えば、原子力潜水艦を数隻保有するのも一つの選択肢である。だが、今はその議論さえできない。これは由々しき事態だ。政策の中身以前に議論が禁じられている。
どうも日本は自縄自縛に囚われているようだ。原潜保有の議論解禁は諸外国へのシグナルにはなり得る。
抑止力をめぐる議論の中で奇特な意見を目にした。「敵基地への反撃能力を持つとは、敵がこちらを叩くことも認めることになる」というのだ。
日本にとって当面の脅威である中国はすでに攻撃能力を持っている。明らかなことだ。それを持っていないと思い込むのは勝手だ。だが、それは危機に直面したダチョウが砂に顔を突っ込んでいるのと大差ない。見ないで済ませられれば、ないのと同じと言い切れるだろうか。
2月24日は記念日にし、平和について国民的な議論をする契機としてはどうか。
ABCやNBC、CBSといった米国のテレビ局発のニュースはいずれも民主党政権の息のかかった情報で占められている。そうした報道をただ鸚鵡返しにしていればいいのか。台湾の友人たちの反応は大切なことを教えてくれた。
台湾の企業は着々と手を打っている。工場の移転に踏み切り始めた。中国本土から手が伸びる前に行動に移す。これも地政学に基づいた判断である。
台湾企業は感情や「教義」とは一線を画し、冷静に行く末を見つめて舵取りをしている。日本政府は地政学の知見を織り込んで国家を動かしているだろうか。
地政学の根本的な原理が猿山の力学と何ら変わらない。そうは認めたくない気持ちは私にもある。だが、現実問題として歴史は繰り返されてきた。
猿山の出来事も歴史も自然の摂理なのだろうか。自然はどう作られているのか。その美しさに見入るとき、ふとそんなことを思う。
規則性のあるものに対して無意識に「美しい」と感じる。人間にはそうした性質がある。自己相似性(フラクタル)もその規則の一つだ。自己相似性とは空間や図形の一部分を構成する形と全体を構成する形が似ていること。自然界をはじめ、図形や音楽、映像など、さまざまな場面で見られる。
「対数螺旋」もその一つだ。自然界によく見られる螺旋の一種で、隼が獲物に近づく際の飛行やオウム貝の殻、寒冷低気圧、渦巻銀河など、さまざまなところで観察できる。対数螺旋は定義式で表せる。私はクラシックギターを趣味の一つにしている。バッハの曲を弾いているときなど、旋律が螺旋状に天上から降ってくるかのような感覚に捉われることがある。人間を陶然とさせる音楽。まさにフラクタルだろう。
フラクタルは「一瞬の中に永遠がある」という仏教の哲理を思わせる。人間は同じことを繰り返している。釈尊はそう教えているのだろう。
「暴力反対」と叫ぶ人たちが暴力について学んでいるわけではない。『独裁体制から民主主義へ-権力に対抗するための教科書』を著したジーン・シャープはどこかマーケティング的な視点を忘れずに「非暴力とは何か」を追求した。
平和を願ってやまない人々もお題目を唱えているだけにしか見えない。零戦はなぜ落とされたかを省みることは決してあるまい。状況分析をして、最も費用対効果の高い道を探る。そんな「平和運動」があってもいいのではないか。
2月24日、私は何を考えよう。台湾の友人たちとは寄って立つところが違う。私は土着の日本人である。日本がここにあって滅びない。その方法を考えなければなるまい。
文明の火を消さずにながらえていくためには、防衛や医療、食料、エネルギーの自立を目指す必要がある。
日本人はどこか付和雷同に走りやすいところがある。
あらゆる理想論は大切にすべきだ。だが、決してそれに支配されてはいけない。共産主義もそうだし、宗教もそうだろう。憲法が尊ぶ平和主義も同じだ。理想はいつもリアリズムから遠く離れている。
松下幸之助が遺した至言を引いておく。「神仏は尊ぶべし。決してこれに頼るべからず」
彼が「マーケティングの神様」と崇められる理由がよくわかる。松下の真髄が現れている一言だ。
空理空論に頼っていたら、いずれ滅んでしまう。
生き延びろ、日本。
Photo licensed under the CC0 1.0.