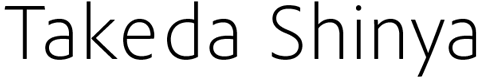新年のお楽しみといえば、何と言っても年賀状である。年に一度、親戚や友人の近況を確認できる。
最近では「年賀状じまい」という言葉も聞かれるようになった。ここ数年、私も年賀状の数をかなり減らした。
年齢を口実に「お義理」で出していた方々には遠慮させていただいたのだ。
インターネットを利用した新年のあいさつも定着している。動画を撮影してSNSにアップする人もいるようだ。
中でも海外の友人からの年賀状は格別だ。今年も何人かとやり取りをした。
台湾の友人もその一人だ。例年なら、大勢の仲間で会食をしている写真などが添えてある。能天気なものが多かった。
その点は私もほぼ同類。年末を過ごすことの多い金沢で前田利家公の鎧兜を前に撮った写真付きの賀状を送ったこともある。
文面ではお互いに「今年はどこの美術館に行ったか」といった他愛もない報告をしている。夫婦ぐるみの付き合いだ。
「君子の交わりは淡きこと水のごとし」という。気の置けない間柄ではあるが、お互いに深いところまでは立ち入らない。そんな交際を続けてきた。
だが、今年は趣が違う。どこか暗いのだ。
理由はすぐに思い当たった。昨年のロシアによるウクライナ侵攻以降、台湾の人々は世界情勢に過敏になっている。恐らくはそのことが影響しているのだろう。
日本にいると、なかなか気がつかない。むしろ、私たちは危機感がなさすぎるのではないか。台湾ではウクライナの次に起こる国際紛争を「我がこと」として深刻に受け止めている。
台湾で一定水準以上の暮らしをしている人たちの中には子供を米国に留学させている人が少なくない。一方で北京に子供を送り出している人もいる。
「国は滅ぶかもしれない。しかし自分の家族は生き延びてほしい」、彼らは事もなげにそう言ってのける。生き延びるための選択を厭わない。
彼らの目に日本の現状はどう映っているのだろうか。私たちはあまりに呆けすぎてはいまいか。あまりに危機感を欠いた姿に「日本は大丈夫か?」と心配されている恐れさえある。
現実には脅威が日々迫っているのかもしれない。だが、そうした情報は国内の主流派メディアからはまず得られまい。
台湾の友人からの便りに満ち満ちていた切迫感。ウクライナの情勢から彼らは何を受け取っているのだろう。
中国共産党の指導者は台湾の価値を知り抜いている。乗っ取りを図る際には世界一とも謳われる半導体工場は居抜きで手中にしたいはずだ。ミサイルの打ち方一つとっても、周到な準備をするに違いない。
事によると、武力一辺倒ではない手法を考えている節さえある。台湾を内部から作り替え、共産党シンパにしてしまう。これができれば、確かに上策ではある。習近平とその側近たちは台湾の選挙結果を注視し、政治的動向を見極めようとしていることだろう。
よく知られているように、台湾に住む人々は大きく2種類に分けられる。本省人と外省人である。
本省人とは1945年10月25日の「台湾光復(台湾島・澎湖諸島での日本による統治が終わり、中華民国に編入されたこと)」以前から台湾に住んでいた漢民族を指す。外省人は台湾光復以降に中国大陸から移り住み、台湾人となった漢民族の人々だ。
人口構成比でいえば、本省人は86%、外省人が12%をそれぞれ占めている。この他に漢民族の移住以前から住んでいた原住民も2%存在する。
複雑な内部構図を持つ台湾。ここでウクライナ政府がしたように、「ロシア軍を呼び込む」ような政治行動がなされれば、どうなるだろうか。
戦火が開かれて1年近く経った今でも、ゼレンスキー大統領を選んだことと、彼の言動に疑問符をつける向きはある。
「親露風」を装う飾りのような指導者を担いでおけばよかったのに。そんな視線だ。台湾ならなおさらだろう。
台湾初の女性総統・蔡英文は昨年11月の統一地方選挙での民進党惨敗を受け、党主席辞任を表明した。今後も中国との関係において台湾ならではの知恵を絞ってはいくだろう。だが、香港で起きたことを私たちはすでに知っている。明るい未来を描くのは難しい。
台湾の統治について私があれこれ言うことの非礼はわきまえているつもりだ。
「中国共産党の奴隷になってください。そうすれば、こちらに火の粉が飛んでくることはない」
そう言っているに等しい。だが、これは現実の問題なのだ。
友人の便りから台湾の抱えるのっぴきならない事情に想いを馳せていると、今度は我が国の外交で思わぬ動きが出来した。
岸田文雄首相が1月11日、スナク英首相と会談。「日英円滑化協定」を締結したのだ。この協定は自衛隊と英軍がお互いの国で共同訓練を行う際の出入国の手続きや部隊が事件・事故を起こした時の対応など、法的な地位をあらかじめ決めておくものである。
日英両国は2022年12月にもイタリアを交えて次期戦闘機の共同開発を決めている。11日の日英首脳会談を前に英首相官邸は報道発表で次のように強調した。
「日英同盟を締結した1902年以来、最も重要な防衛協定」一部のメディアは早くも「日英同盟が100年ぶりに復活」とはやし立てている。
これに先立つ動きにも私は注目していた。2022年10月22日、日本はオーストラリアと安全保障協力を深化させる新たな共同宣言に署名している。事実上、日豪両国は「準同盟」関係を結んだに等しい。だが、それほど大きくは報じられなかった。
1950年代以前から形成されてきた「ファイブアイズ」と呼ばれる国際的な機密情報共有の枠組もある。米英両国が立ち上げたものだ。現在はカナダ、オーストラリア、ニュージーランドが加わっている。米国以外は英連邦の構成国である点が特徴である。日本はこれらの5カ国と安全保障面で協力を進めてきた。
オーストラリアは「英国」である。これは私の実感だ。かつて英連邦の一員であったのだから、当然ともいえる。
ある会合でメルホルンを訪れたことがあった。出席者は世界各地から集まってくる。共通しているのはそれらの国々はいずれも紙幣や切手にエリザベス女王の肖像を刷り込んでいる点だ。彼らは英連邦の旧構成国。いわば同胞であり、独特な親密さを抱き合っている。
一口に「英国」といっても、指し示す内容にはいくつかの階層がある。最も狭い意味ではイングランドのみ。そこにスコットランドやウェールズ、北アイルランドを加えると、「グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国」となり、これも「英国」である。
英連邦も広義の「英国」といえる。旧大英帝国の版図であった56の加盟国から構成され国家連合で、英語では「コモンウェルス・オブ・ネイションズ(略称:コモンウェルス)」となる。
加盟国は北米をはじめ、アジア、オセアニア、アフリカにまたがり多数存在する。その大半が英語を公用語としており、気脈を通じている。同じ西欧列強の植民地でも、フランス統治下だった国々とは全く異なる文化を持つ。
話を2022年10月の「日豪同盟」締結に戻す。オーストラリア側の報道では実質的には「安全保障条約」であると喧伝されていた。日本ではそれほど騒ぎになっていない。1960年、1970年前後の日米安全保障条約改定とは大違いである。
今回の「日英同盟」でも大反対の声が巻き起こったり、国論を二分したりするような事態には至らなかった。これは多分に英国の外交力に負うところが大きいのではないか。
日英同盟と聞くと、思い出すことがある。同盟条約に両国が署名したのは1902年1月30日。ロンドンの英外務省で行われた調印式に出席した英国代表はソールズベリー侯爵内閣の外務大臣第5代ランズダウン侯爵ペティ=フィッツモーリス。日本側代表は林董特命全権公使だった。ここで詳しく述べることはしないが、林は私にとって単なる歴史上の偉人ではない。特別な存在である。
日英同盟でもう一つ思い出すことがある。1997年に刊行されたスパイ小説『誇り高き男たち』だ。作者は『深夜プラス1』で知られる英国冒険小説の大家ギャビン・ライアル。20世紀初頭、英国の石油利権に多大な影響を与えるドイツによるバグダード鉄道建設を妨害する密命を帯びて諜報活動に身を投じる英軍将校の物語である。ほぼ同時期の中東が舞台で英軍人が主人公と共通点の多い映画『アラビアのロレンス』にも匹敵する傑作と言っていい。 『誇り高き男たち』はフィクションだが、バグダード鉄道計画そのものは史実だ。19世紀末から20世紀初めにかけてドイツ帝国が「3B政策」の一環として推進した。3B政策とはベルリン、ビザンティウム(イスタンブールの旧称)、バグダードの3都を鉄道で結ぶ長期戦略だ。
バグダード鉄道はオリエント急行のような旅情や憧憬を醸し出す対象では決してない。沿線には第二次世界大戦後、独立を果たした産油国が並んでいる。原油を積み込んだ貨物列車をドイツ本国へとなだれ込ませる仕掛けであり、産業政策である以上に軍略の側面が強い。
『誇り高き男たち』の主人公は英軍人であり、作者も英国人。英国で刊行された小説である。英国びいきの視点で貫かれている。バグダード鉄道計画は好ましからざるものであり、それを阻止しようとする主人公の行動は正義として描かれる。
日英同盟締結のわずかばかり前、ドイツが石油を大量に安価で国内に持ち込めるラインを計画した。英国にとっては覇権を維持する上での妨げでしかない。ドイツが欧州大陸で台頭する事態はなんとしても避ける必要がある。ドイツの動きは看過できない。英国の執念が第一次世界大戦の遠因となった。自らの覇権が危うくなると、武力に訴える。英国とはそういう国だ。一触即発の国際情勢の中、日英同盟は結ばれたのだ。
第二次大戦後、植民地のほとんどを英国は手放した。今後の英国の発展を考えると、英連邦を基準に考える必要がある。
その際、日本に果たせる役割はあるのか? それは何か? 慎重かつ周到に検討した結果、今回の「日英同盟」が結ばれのだろう。決して英国の国力伸長の邪魔にはらない。にもかかわらず、利用価値は十分にある。
具体的に言えば、こうだ。英連邦の安全保障を補完する上で日本の貢献度は小さくない。オーストラリアやインドの協力を得ながら日本も巻き込む。そう考えると、スナク首相の両親が1960年代に東アフリカから英国に移入したインド人であることはなかなかに興味深い。
こうした思惑の下、今回の「日英同盟」が実現した。
米国のシンクタンク、=「戦略国際問題研究所(CSIS)」は1月9日、2026年に中国が台湾に上陸侵攻作戦を行ったと想定し、24通りのシナリオを検証した報告書を公開している。
台湾有事は今ここにある危機である。2022年の日豪同盟に中国は強く反発した。台湾政府は歓迎している。日本ではあまり報道されていない事実だ。もっとも国内主流派メディアが世界の実情を伝えないのは今に始まったことではない。
では、英国との「同盟関係」を今後どう考えていけばいいのか。私は必ずしも悲観ばかりしているわけではない。日本が上手に立ち回れれば、今後のV字回復への端緒ともなり得るとさえ見ている。
日米安保で日本がどれだけ経済的な恩恵を被ったか。私たちの世代は十分すぎるほど知っている。
今回の「日英同盟」には米国も不快感は示していない。東アジアにおける中国の動きを牽制するための防衛協定だ。もとより反対などするわけがない。
北朝鮮の核は現在、日米両国にとって懸案となっている。だが、米国にとって問題なのは核爆弾を搭載した大陸間弾道弾が自国に飛来すること。何らかのチャネルを通じて朝鮮労働党側から「標的にはしない」と確約が取れれば、北朝鮮の核保有は憂慮すべき対象ではなくなる。もっとも北朝鮮の「確約」がどこまで信頼に足るかはまた別の問題だが。
新型コロナウイルス感染症への対策を見ても、中朝の感覚は特異であることがわかる。死者ゼロと言っていたのが、一夜にして6万人に変わるのだ。「白髪三千丈」「万里の長城」といった形容でもわかる通り、中国では数字はあくまで感情表現の道具でしかない。
日英同盟は日本にとって新たな地平線となる可能性を秘めている。日本の若者はあまり海外に出て行きたがらない。だが。向かう先ができたとも言える。
今後の日本はどうやって飯を食っていくか。この課題にも同盟は一筋の光を示してくれている。
英国にとってアフリカは「ちょっと南にある庭」のようなもの。英連邦はこれからその庭を耕していく。
アフリカ大陸はなかなかに耕し甲斐のある庭だ。耕す過程で世界を富ませていく。環境を壊さずに開拓していく技術を日本は持っている。食料や農業、医療にまたがる知恵をアフリカは必要としている。
日本を豊かにし、アフリカも豊かにする。そのサイクルの中で日本を道具として使う。同盟を結ぶに当たって英国はそう考えたのかもしれない。
自民党の国会議員にも親中派がかなり増えた。一説にはすでに3分の1ほどを占めるともいわれている。
林芳正外相を筆頭に岸田内閣の顔ぶれにも親中派は少なくない。中国べったりの二階俊博前幹事長も岸田氏を「全力で支える」と公言してはばからない。政権中枢には中国に関する際どい情報も入ってきているはずだ。だが、首相やその周辺が「中国発の危機」に言及することはない。
英国が日本との「同盟」に踏み切ったのは危機に直面しているとの認識があるからだ。以前のコラムで触れた独露間のパイプラインの話に似ている。
100年前、英国はドイツの覇権を阻止するために日英同盟を結んだ。ウクライナのパイプラインを爆破してから3年後、同じように日本と結ぼうとしている。英国外交の原則は世紀をまたいでも基本的には何ら変わっていない。第一次大戦は勃発当時、すぐに終わるものと見られていた。だが、みるみるうちに規模が拡大。日英同盟締結後の世界はろくな方向に向かわなかった。
2022年にウクライナで火ぶたが切られた戦争。これから台湾に飛び火し、さらに加熱しない保証はどこにもない。
世界はかなりきな臭い状況にある。危機は差し迫っているのではないか。新年早々そんなことを感じてしまった。台湾有事となっても、米中両国が中心部に核を打ち合うようなことにはならない。割りを食うのはウクライナ同様の「緩衝国家」である。米軍の基地は台湾にはない。沖縄をはじめ、日本国内にあるのだ。
将来、歴史を振り返ってみた際、「あそこが分岐点だった」と指摘される。2023年はそんな年になりそうだ。
我が家の家訓を引いておく。
「稚心を去れ」
「稚心」とは子供の心。それを捨て去る。つまり、「自立した大人として生きていく覚悟を持て」というほどの意味だ。
「稚心を去れ」は幕末に活躍し、安政の大獄で倒れた福井藩士・橋本左内が遺した言葉である。佐内は混迷を極める政局にあって、西欧の先進技術の導入・対外貿易の必要性を説き、帝国主義と地政学の観点から日本の安全保障を論じた。
依存や従属とは決別したい。今年こそ、その第一歩となるだろうか。
Photos licensed under the CC0.