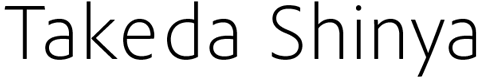「ムーアの法則」をご存じだろうか。
大規模集積回路(LSI IC)の製造・生産における長期傾向について論じた指標。
経験則に類する将来予測でもある。
米インテル社の創業者の一人であるゴードン・ムーアが1965年に論文で発表した。
当時、彼はフェアチャイルドセミコンダクターに所属していた。
ムーアは集積回路あたりの部品数が毎年2倍になり、この成長率は少なくともあと10年は続くと予測した。
この予測は関連産業界を中心に広まっていった。
1975年には次の10年を見据え、2年ごとに2倍になると修正。
彼の予測は75年以降も維持され、それ以来「法則」として知られるようになった。
ムーアの法則は「指数関数的発展」の代表例として知られる。
大雑把に捉えると、ここ半世紀ほどの間、科学技術は指数関数的に進化を遂げてきた。
ムーアの法則を拡大解釈すれば、大方の問題はいずれ解決していくことになる。
「こうなったらいい」と私たちが空想することはタイムラグはあっても、いずれ実現する。
新型コロナウイルスが変異を続けても、やがてワクチンや治療薬は開発される。
かつては助からないと思われていた心臓病も、臓器移植の技術が向上し、お金をかければ治る見込みができてきた。
いずれはiPS細胞を活用して必要な臓器を創出する時代が来るのかもしれない。
科学技術の発展はまさに指数関数的。人間の予想を超えて時に爆発的に進んでいく。
もちろん、未来予想はそれほど簡単ではない。
予測ができないこともあるし、裏切られることも少なくはない。
ただ、ムーアの法則を見る限り、「大いなる楽観論」を必ずしも捨てる必要はなさそうだ。
未来を考える上で悲観的な条件だけを並べ立てるだけが得策ではあるまい。
「何とか解決していけるのではないか」と楽観を基底に置く。
私自身も物事をあまり無神論的には見ない。
「最終的には悪い方向には行かないだろう」という思いが根底にある。
これからも姿勢を変えるつもりはない。
そんな私でも、この国の今後を考えると、暗澹たる思いに駆られるときがある。
岸田文雄首相と政府は何をしているのか。
目の前の些事にとらわれ、モグラ叩きに汲々としているばかりではないか。
背景には国民世論の批判を過度に恐れる心性がある。
恐怖に突き動かされ、日々の政権運営を行っているとすれば、覚束ないのも無理はあるまい。
仮にも世界第3の経済大国を舵取りするのだ。
「こうあってほしい」という願望は少なからずある。
だが、現実の内閣の姿はそれには遠く及ばない。
経営者に最低限必要な資質は「30年後を見通す能力」である。
これを欠いたトップが率いる会社は立ち行かなくなる。
国の指導者ともなれば、なおさらだろう。
せめて長期的な展望くらいは持ってほしいものだ。
長期的展望に立った際、まず確実に外れない指標が一つある。
人口統計だ。
現在でこそ、少子化は重要な課題と認識されている。
だが、よく知られている通り、この問題は昨日今日降ってわいたわけではない。
以前から指摘されていたが、何ら有効な手を打てないまま今日に至った。
私が広告代理店に勤務していた頃、大手タイヤメーカーと付き合いがあった。
この会社は先行きの見通しという点では誠に優れた社風を維持していた。
「厚生労働省が発表する人口動態統計など当てにならない」と、独自のルートで人口の推移を調査。
その上で施策を立案し、実行していった。
代表的なものが生産拠点の東南アジア移転である。
まさに先見の明と評するにふさわしい英断だった。
その後のASEAN5(インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム)の躍進ぶりは誰もが知るところだ。
繰り返しではあるが、30年後を見据えていないリーダーに存在価値はない。
では、30年後、先進諸国の人口はどうなっていくのか。
これも繰り返しだが、人口の推移ほど間違いのない指標はない。
フランスの人口統計学者エマニュエル・トッドが2000年〜2050年における各国の人口の動態を自著で紹介している。
英国は25%、フランスは11%の増加。
これに対し、ドイツは2.5%、ロシアは7%の減少。
中国は0%で変化なし。
トルコは53%、イランは58%と、大幅に増加する。
欧州の政治を中止し続けるトッドにとって、英仏独やロシアはもちろん、トルコやイランの動向は気になるところだろう。
少子化の傾向から抜け出せない日本は17%の減少。
突出した数字だ。米国はといえば、34%の増加である。
日本外交は同盟国である米国を頼りにしてきた。
お人好し過ぎると感じられるまでに頼りきった挙げ句、人口は大幅減。
一方の米国はちゃっかり3割以上も増加している。
これはまごう方なき30年後の姿である。
2050年代、日本の人口は1億人強でイランとほぼ同じになる。
核を保有する軍事大国であるイランほど、国際社会で存在感を示せるだろうか。
日本は国策としてどんな分野に力を入れていくべきか。
国の未来像を模索する上で人口減少という不都合な真実から目を逸らすわけにはいかない。
米国の主要産業といえば、今や軍需と情報通信、そして金融である。
昨今はやりの金融工学の理論に支えられた金融商品は「カネからカネを生み出す」ものだ。
米国は他人の懐に手を突っ込んで、平気でかき回すような真似で稼いでいる。
その弊害の最たるものが2008年のリーマンショックだった。だが、彼らは懲りてはいない。
ましてや30年後には人口が3割増しなのだ。
私たちの同盟国はその分、強欲になっていることだろう。
現行の外交政策を変更しない限り、日本は米国の顔色をうかがい続けることになるだろう。
つまりは強欲ぶりに寄り添っていかなければならない。
具体的にはこれまで以上に国債を引き受け、「構造改革」の要望に応えていくということだ。
対米追従ばかりが外交ではない。
「米国が駄目なら、中国がある」と主張する人もいる。だが、巨大な隣国は30年後も変わらぬ人口を維持している。
世界の食料を食べ尽くす勢いは衰えまい。
食料安全保障を考えた場合、手を携えていけるだろうか。
30年後の日本では生産年齢人口比率が50%にまで低下する。
人口ピラミッドでもっとも高い山を描くのは70〜80歳台。
生産年齢人口比率が7割だった1990年と比較すれば、違いは歴然としている。
同盟国には頼れない。隣国とも手はつなげない。
となれば、答えは明白だ。自国の食いぶちくらいは何とかしなければならない。
これまで私たちは農業や水産業を疎かにしてきた。
日本は米国の小麦を買うだけの国に成り下がっていたと言ってもいい。
自分が乗っている船の底に穴を開けているようなものだ。
食料自給率を上げるべきというと、すぐに反論する向きがある。
「国土が狭すぎる」というのだ。
だが、果たして本当にそうだろうか。
今こそ、我が国の第一次産業においてムーアの法則を信じるときではないのか。
少々古い話にはなるが、1985年の国際科学技術博覧会(つくば科学万博)で見た光景は今もまぶたに焼きついている。
1万3000個のトマトを実らせた巨木が展示されていたのだ。
土を使わない水耕栽培。トマトにストレスを与えずにのびのびと育てる。
農業生産技術に携わってきた先達の経験や書籍に学び、植物としてのトマトの原理原則に則って、栽培管理をしていた。
生命力を信じる技術がそこにあった。
生かすことで、生かしてもらえる。
そんな農業に国を挙げて取り組むべき時ではないのだろうか。
人口減少の傾向も食料自給という観点では追い風となる。
まんざらできないことではない。
米国からの小麦の輸入には目をつぶったとしても、最低限生き延びる努力はしていくべきだろう。
食料だけではない。
防衛や医療、エネルギーも含めた4分野で日本は自給率をさらに上げていかなければならない。
知恵を使えば、きっとできる。
「アベノミクス」と呼ばれる「経済政策」で我が国は異次元緩和に踏み切った。
それがどれほどの影響を日本経済にもたらしたのか。
恐らくは本格的な総括がなされることはもうないのだろう。
「アベノミクス」が目指したのは「架空の富」だ。
額に汗して頑張る美風を思い出したい。
努力を怠らなければ、科学技術は指数関数的に発展するのだから。
目先の数字をいじるのはやめにしよう。
日本の伝統を思い起こすことだ。
今、忘れられているものは何か。
唐突かもしれないが、私は「士農工商」だと見ている。
江戸時代、商人の地位は低かった。
今や「商工農士」の時代だ。
一時凌ぎで数字の均衡ばかりに注力している。
「士農工商」のうち、士つまり武士階級は生産には従事していない。
彼らが担っていたのは「志」である。
「士農工商」とは志に始まり、農(食料生産)、工(実体経済)と来て、商は一番下に置かれた。
現在、トップに位置する商とは金融工学的なカネがカネを生む構図だ。
いわば、「花見酒の経済」である。生き馬の目を抜く国際社会で果たして生き残れるだろうか。
今こそ方向転換すべきだ。
縄文時代の昔から日本が培ってきた生命哲学に信を置き、1億の民を食べさせるために必要なものを生み出す。
これは世界貢献にもつながる道である。
「士農工商」を忘れた日本人はいつの間にか志も失ってしまった。
志のない国に公の心は育たない。
結果として、「今だけ、金だけ、自分だけ」といったさもしい風潮ばかりがはびこる。
農業分野での技術革新に向けて兆円単位の予算を配分する必要がある。
農業における技術とは何も農薬や化学肥料をまき散らすことではない。
70年以上前、米国は日本人にコッペパンと脱脂粉乳の学校給食を押し付けた。
自国の小麦を消費させるためだ。
白米に納豆、地どれの野菜といった日本の食文化は脇に追いやられ、パン食が根付いた。
一方で稲作農家は淘汰されていく。
だが、米国による食料供給体制は持続可能な仕組みではない。
人口増加で国内の状況が変われば、平気で売り止めに転じるだろう。
いかにもマーケティング発祥の国らしい立ち居振る舞いではないか。
人口増加で食料の国内消費が増えれば、同盟国であっても助ける必要はない。
「自国ファースト」は国際標準である。
政治家もメディアや世論のバッシングを恐れている場合ではない。
真の恐怖は30年後の国の姿にこそ感じるべきだ。
国民を飢えさせる事態は何としても避けなければならない。
人々に飯を食わせることこそ、政治にとって最重要な役割だ。
中国海軍の増強がニュースになる。
だが、そのことが何を意味するかは必ずしも正確に伝わっていない。
日本周辺の海洋資源が横取りされかねない。これは現実だ。
国際社会において食料や資源は武力を背景に奪い合うものに他ならない。
至るところに可能性は転がっている。
昨日の延長線上に未来はない。
発想の転換と行動こそが求められている。
今度こそ二の足を踏んではなるまい。
Photos licensed under the CC0.