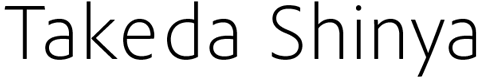「やられた」
決定の報を聞いた際の率直な感懐である。きな臭いものはとうに感じていた。
7月20日に行われた新型コロナウイルス感染症(COVID–19)の治療薬・ゾコーバの薬事承認を議論する薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会と薬事分科会の合同会議。継続審議となった。
COVID–19はこの夏、第七波と呼ばれるピークを迎えた。テレビや新聞は連日、首都圏を中心とする感染拡大を報道。重症化した患者が出る一方、医療機関の病床には空きがない。何度目かの医療逼迫が我が国を襲った。
第七波に向けて政府は行動制限をしない方針を打ち出した。
現場で「門番」の役割を果たさなければならない医療従事者の苦労はいかばかりだろうか。
彼らにとって新しい治療薬は一筋の光明だった。私の知人である医師もその一人だ。
「新薬が承認され、私の診療所に入ったら、ああしたい。こうもしたい」
そんな具体的な話を聞かされていた。「取らぬ狸の皮算用」と嘲笑する気にはなれない。野戦病院を思わせる現在の医療体制の最前線で奮闘する彼にとっては切実な問題だった。
報道によれば、承認が見送られたのは有効性を「推定」できるだけのデータが揃っていないからだという。
会合でも「緊急に承認したとしても医療現場で使われる見込みがない」とする意見が続出した。
急速な感染拡大を受け、緊急承認を容認する意見もなかったわけではない。だが、米製薬企業の飲み薬2種類がすでに実用化されていることも手伝って、最終段階の治験データを待つという結論に至ったようだ。
確かにゾコーバの効果には曖昧な部分も少なくない。ただ、はっきりしていることもある。
ウイルスの量を減らすという点だ。
ゾコーバが承認されれば、例えば、こんな対処が可能になるはずだった。
発熱外来に「COVID–19かもしれない」という患者が来たとする。まずはカロナールなど、すでに効果が実証されている解熱剤に加えゾコーバを処方するのだ。これだけでも立派な治療にはなる。ワンパターンであっても、効果は見込めるだろう。
だが、承認の見送りで知人医師の目論見は絵に描いた餅となった。彼以外にも落胆している医師は他にも大勢いるはずだ。
現場の医師にはCOVID–19と戦う武器が不足している。これまでの経験でなんとかするしかない。
現実に第七波で取られた方策は「自宅待機」だった。それが妥当であったかどうかの正確な評価は後世の検証を待たねばならない。
今回の審議には一つ新しい趣向が凝らされた。会合の模様をインターネット上で公開したのだ。残念ながら、アーカイブは残されなかったものの、議論がオープンになったことの意義は計り知れない。
厚生労働省が公開している資料から出席者の顔ぶれを確認してみた。医学・薬学を中心に東京大学や京都大学、慶應義塾大学などの出身者が目に付く。日本における現時点で最高の知性が招集されているのだろう。素人目にもわかることだ。
では、それらの碩学による実際の議論はどうだったのか。ネットを通じてライブを視聴した感想を述べてみたい。
大きな流れを作ったのはネガティブキャンペーンもどきの後ろ向きな意見の数々だった。
ついつい米大統領選挙を想起してしまったほどだ。
「効果がはっきりしない」
「他の薬品との併用ができない」
「妊婦が服用すると奇形児が生まれる可能性がある」
そうしたことばかりをあげつらう。
審議会の模様を伝える新聞の中にはゾコーバを指して、
「救世主にならない」
と見出しを打った記事もあった。
確かに審議会の立て付けは救世主を求める趣旨のものではないだろう。それにしても、あそこまで否定的な見解ばかりが続出したのはなぜなのか。
今回の承認は通常のルールではなく、緊急承認制度に基づくものだ。
「緊急承認する必要があるのか」
そうした声がネガティブキャンペーンにより拡大され、「審議継続」の結論を導くに至った。結果として誰も責任を取っていない。少なくとも私にはそう見えた。
言うまでもなくCOVID–19は国家的な危機である。いまだに収束の道筋さえ見えていないこと自体がリスクと言っていい。
出席者にはどこまでその認識があっただろうか。国家のリスクを回避するより、自分の身を守ることに軸足を置いている。誠に失礼ながら、そう見える方も何人かおられた。
保身のため、有事にもかかわらず真っ当な議論すらできない。公益に尽くすべき義務感や責任感はどこへ行ったのだろうか。
東大や京大を頂点とする戦後教育を受けたエリートの集団。彼らの習性の一端がよく見えた会合でもあった。ある意味ではこの国の形を表していたのかもしれない。
専門家が自らの知見に基づき、危惧する点を述べる。そのことには何ら問題はない。
だが、現場で診療に当たっている医師たちは専門家の知らない現実を見ている。COVID–19の感染拡大がどういう状況にあるかは彼らに聞くのが手っ取り早い。
ゾコーバをあげつらうのもいいが、出席者たちに医療機関や医療者の置かれている現状への洞察力、想像力がどこまであったか。はなはだ疑問だ。
最高の知性の持ち主には現場感覚が欠如している。現在のこの国の形を示す象徴的な事例の一つだろう。
悪口を気持ちよくまくし立てれば事足りる。学界の権威が担うべき役割とはそこまで軽いのか。
戦後教育の勝利者であり、最も有能な層に属するであろう彼らによる議論が今回のような形で進んでいく。日本の断片を切り取って見せられた気がした。
誤解を恐れずに言えば、彼らを教えていた先生たちの世代に思いをいたした。彼らが受けていたのと同等の教育を今日のエリートも受けていればどうだったか。
国家としてどう考えるか。公の人間としてどう考えるか。そうした原理原則に立脚した議論が聞けたはずだ。
逼迫する医療現場を支援するにはどうすればいいのか。あげつらうことの喜びに負けて質が高いとは言えない議論に終始している場合ではあるまい。
何のために緊急承認制度を設けたのか。これでは甲斐がないだろう。
法律や制度は本来、人間を救うためにある。その原点に立ち返るべきではないか。
大学や研究機関で地位を得てしまうと、自分ごととして考えるのが難しくなってしまうようだ。
民主主義は個人主義に通じる。この国のエリートたちは全体を見通す力を失っている。これは戦後教育の欠陥だろう。
連合国軍総司令部(GHQ)にしてみれば、思い通りの結果ではないか。宗主国の「傭兵」として使い捨てるには格好のメンタリティーを持った優秀な人材が育っているからだ。彼らは間違っても祖国のことなど考えはしない。
緊急承認を見越してゾコーバを開発した塩野義製薬にはすでに政府から100万人分の注文が入っていたという。現在使われている外資の薬は200万人分を購入済みだ。利益を享受しているのはファイザーをはじめとするメガファーマである。
マーケッターとして感じることもある。ゾコーバのような薬が承認され、安定供給されるようになれば、COVID–19は「2類」に置いておくわけにはいかない。「5類」に変更しなければなるまい。
それでは困る既得権益層がいる。COVID–19があるから収益性を保っている。COVID–19のおかげで成り立ち、食べていける。そんな機関がいろいろとあるのだろう。
現場の医師が打ちひしがれる一方、今回の継続審議でほっとしているお役人もいるはずだ。
現場力のない指導層はこれまでにもこの国を目には見えない形で蝕んできた。これからもそれは続くのだろう。
その点、明治国家の官僚は強かった。彼らの多くは幕末に武士だったからだ。
現実に戦争を経験していない者が行政に携わると、どうしようもない虚弱さが見え隠れすることがある。もちろん、軍人出身であれば、なんでもいいというわけではない。知恵を生み出す根本には現場経験がある。そう言いたいだけだ。
評論家の寺島実郎氏はCOVID–19の世界的な感染拡大以降、「全体知」という概念を提唱している。未知の問題を解決するのに欠かせない全体知とはどのようなものなのか。
寺島氏によれば、専門家による「専門知」、複数の専門知を集積した「総合知」をさらに一段階深めたところに全体知はあるという。
仏教学者・鈴木大拙の「外は広く、内は深い」という言葉は全体知を言い表している。寺島氏の理解では、内の深さと外の広がりに対して柔軟に感じ取る力を持つこと。それこそが全体知の入り口だという。
だが、全体知的なものは何も寺島氏の発明ではない。同工異曲ともいえる考え方は世界各地にある。
我が国も例外ではない。かつては「お天道様は見ている」といったものの見方があった。
英語圏には「オールシーイングアイ」という慣用句もある。「全てお見通しの目」とでも訳せばいいのだろうか。
全体知的な概念は言葉や文化の壁を超えた人間の知恵と言ってもいいだろう。
それほど人間になくてはならないものであったはずの全体知。肝腎要の要素を失った日本はどこへ行くのか。
今こそ根本に立ち返るべきだ。危機に際して本当はどうすべきなのか。
信条すら定かでないまま、質の低いキャンペーンを張り、発言を繰り返す。誰にとっても良いことではないだろう。
国家を構成するのは自立した個人のはずだ。
現行憲法を改正する以前に個々人の中にある「心の憲法」を作り直す必要がありそうだ。
まずはそこから始めてみてはどうだろう。