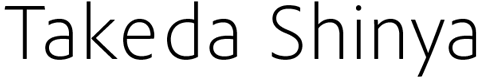前回のコラムではパイオニアで販売促進の任についていた頃の話をさせていただいた。当時を振り返っているうちに思い出したことがある。今回はそれに触れておきたい。
パイオニアはもともとカーオーディオのメーカーだった。言うまでもなく、カーオーディオは車の一部。部品の一つだ。産業構造から言えば、自動車産業の川下に位置すると言っていい。
今から半世紀ほど前、私がパイオニアに関わり始めた頃。自動車にはエアコンがついていなかった。「カークーラー」はオプションの部品として売られていたのだ。後付けで搭載するカークーラーの分野ではクラリオンやサンデンといったメーカーがしのぎを削っていた。
今となっては全てが懐かしい。余談だが、クラリオンでは1975年から30年にわたってキャンペーンガールを毎年選出していた。これがクラリオンガールだ。初代のアグネス・ラム以来、人気芸能員への登竜門として注目を浴びていた。烏丸せつこや宮崎ますみ(萬純)ら、幾多の人材を輩出している。
歴代クラリオンガールの中でも変わり種といえば、第14代の蓮舫だろう。現参議院議員で立憲民主党の前代表代行だった、あの蓮舫である。彼女の写真が載ったクラリオンのカタログが販売店に置かれていたのを今も覚えている。そうした店を回りながら、販促の仕事に携わっていた。
後付けのカークーラーはやがて市場から消えていった。デフォルトで搭載されているのが当たり前になり、必要のないものとみなされたからだ。パイオニアは後付けのオーディオを製造・販売していた。後付けとはいえ、性能・品質は高く、ファンも少なくなかった。本来であれば、カーオーディオは単なる車の部品に過ぎない。だが、パイオニアは品質の高さに加え、それ以上の付加価値をつけた。必需品から嗜好品のレベルに格上げすることに成功。ユーザーの支持を獲得していった。
後付けカーオーディオは今でも売られている。需要はあるということだ。パイオニアはカーオーディオ業界の盟主として、各社がながらえる素地を作った。
当時の私はマーケティングのプロとして、クライアントであるパイオニアに対し、その時々に製品をどう売っていけばいいかを提案・助言する立場にあった。試行錯誤の中で一つの答えが見えてきた。最終的には売り場そのものを変えていかなければならない。新しい販売チャネルを提案し、一つ増やした。それが「コクピット」というチェーン店だ。これはパイオニアとブリヂストンの協力で築き上げた販売網だ。両社とも私の得意先だった。新業態開発を通じて、私は需要創造の提案をしたことになる。
新業態開発についてマーケターに話をさせると、止まらない。どこまでも長くなるのが必然だ。その轍を踏まぬよう用心しながら、ささやかな経験を振り返ってみたい。コクピットの事業を通じ、私は目を開かされる思いを何度もした。「日本にこんな資産があったのか」掛け値なしに驚きの連続だったと言っていい。当時の私は自動車の部品を取り扱う小売業の関係者と次々に面談していた。彼らに提案するのが主な仕事である。
自動車部品はいわば必需品だ。必要なものだけを売っていては、商売の範囲は限られる。なかなか広がってはいかない。
コクピットの主力商品はタイヤ。おわかりの通り、消耗品である。この手のものを買うこと自体は決して楽しいものではない。買い手に楽しさを喚起させられないものを売っている限り、需要が必要以上に伸びることはないだろう。
では、コクピットは何を売るのか。ストーリーである。
「走りと音のプロショップ」当時の私がつけたキャッチコピーだ。ロゴも作った。今まで部品を商ってきたタイヤ屋さんたちに新業態を作ってもらう。これが私の提案の中身だ。必需品を売るだけの日々から彼らに仕事の幅を広げてもらいたかった。タイヤ屋さんがオーディオを売る。口で言うのは簡単だ。だが、そのためにはコペルニクス的な転換が求められる。もっともオーディオも部品には違いない。必需品を売っているだけの商売は決して面白くはないのだ。やや専門的な表現になるが、コクピットの事業には需要を創造する観点が欠かせない。「不要なものを売っている」と売り手が気づいたとき、需要創造の観点が生まれる。そして、当時の日本各地にはまさに需要を創造している小売業が展開していたのだ。戦国時代きっての変革者といえば、織田信長だろう。戦乱の世にありながら、信長は経済政策の重要性にも目配りをしていた。誠に稀有な武将である。
信長が策定した制度の一つが「楽市楽座」だ。この場合の「楽」とは「自由」を指す。当時の商人は市場で商品を売る際、土地の所有者である寺社などにショバ代を払わなければならなかった。そもそも組合に属していなければ、店を出すことさえかなわなかったのだ。信長は楽市楽座によって、税を免除し、誰もが自由に商売できるようにした。結果として町は賑わい、信長は商人たちの支持を集めることに成功した。
最近の研究では楽市楽座が信長だけのアイデアではなかったことが明らかになってきている。各地の戦国大名も同じような施策を講じていた。古くは楽市楽座の時代にまでさかのぼれるのだろうか。日本人には小売りに関する天賦の才があると感じられる。
コクピットの事業が走り出す頃、全国の小売店の中で成功事例がぼちぼち出始めていた。何も最先端のマーケティング理論を持ち出すまでもない。若年層が車を「おもちゃ」として使い始めていた。具体的にいえば、部品をくっつけて楽しむ層がユーザーの中に生まれていたのだ。
そうした動向を先導する人たちは何をしていたのか。繰り返しになるが、ここで一番重要なのはものではなく、ストーリーを売ることだ。需要促進の鉄則はストーリーをいかに売るかにある。
メーカーがそれをやると、どういうわけかある罠にはまってしまう。スペックにこだわり過ぎ、細かな点で競争に走るのだ。
ユーザー向けに「機能一覧」を作り、その中身を充実させることばかり考える。テレビのリモコンを思い出してほしい。一時期、細かいボタンがいっぱい並んでいた。メーカー各社の技術者が入れ込んだ結果である。プロとしては当然かもしれない。彼らの言う「よい製品」とは「高度な機能を有す製品」とほぼ同義である。
だが、ユーザーはあくまで素人。そこまで高度なものは求めていない。結局は使いづらい製品が出来上がってしまうことも多い。
成功を収めている小売業の発想はメーカーとは一味違っている。「その製品を使うと、どんな楽しいことが起こるか」を売っているのだ。これこそがストーリーを売る手法に他ならない。私は日本中を駆け回り、小売店の成功事例を片っ端から取材した。店主に話を聞き、写真を撮る。その上でコクピットのオーナーになり、商売を始める人を対象にしたセミナーで講師を務めた。取材で会った店主たちは決して部品を売ってはいなかった。部品で形作られる生活、彩られる楽しさを売っている。
そのあたりのことを個別に取り上げていくと、きりがない。峠の走り屋たちを主人公とするマンガがヒットし、「峠族」と呼ばれる人たちが各地に出現した。そこから、「あの峠をどれだけの速度で走る」という設定そのものを売る発想が生まれる。車を「峠仕様」にして、「伝説の走り」を再現してもらうのだ。コクピットの商いは部品の販売から次第に遠ざかっていった。コクピットの業態をさらに別の角度から見てみよう。その車を持っていることでどんな自分を演出できるか。ライフスタイルを売っていたと言ってもいい。自動車には車種ごとに異なる世界が広がっている。
例えば、クラウンやセドリックなどの国産VIPカー。チューニングしたり、飾り付けの用品をいろいろつけたりする。その結果、1980年代に米国で大ヒットしたドラマ「特捜刑事マイアミ・バイス」のようなライフスタイルが注目された。はっきりいえば、当時のフロリダあたりで実業というよりは「水商売」で成功を手にした人たちに近い指向性が関心を集めたのだ。当時のマイアミ界隈には金の鎖を腕につけ白いジャケットを素肌の上に着るような人たちが現にいた。車を通して彼らの生き方に近い文化が手に入れられる。そんな価値観をコクピットは売っていた。
車種ごとの世界観は他にもある。ミニクーパーの専門店はミニクーパー独自の世界を、ワーゲンの専門店は「カブトムシ」に代表されるような世界をそれぞれ売っている。国内での成功例といえば、ハーレーダビッドソンの代理店が思い出される。ハーレーは米国では機械の良さをアピールし、ファンをつかんでいる。日本のある代理店は「ハーレーのある暮らし」や「そこからできる仲間」の素晴らしさを打ち出し、多くのファンを獲得した。
このところ、マーケティングの世界ではナラティブアプローチが注目されている。ナラティブとは「話法」「語り口」を意味する文芸の用語。マーケティングにおけるナラティブは「主人公が『あなた』になる形式の物語」を意味する。ロールプレイングゲームのように、自分の選択によってさまざまな分岐を通り、あなただけの結末にたどり着く。そんな物語だ。
どこかの大学教授がまことしやかにナラティブの有効性を説いている。だが、私は何十年も前に現場で目にしていた。この国の小売業は買う主体、「あなた」にコミットしていた。生活者を基盤にした意思疎通が確かに息づいていた。
それを買うことでこれから何が起こるのか。需要を創造する上で核となる部分について彼らは熟知していたのだ。
取材で得た彼らの取り組みを私はコクピットの店主たちに惜しみなく伝えた。ユニークで楽しい店が全国規模でたくさん誕生した。もちろん、売り上げも好調だった。細やかに生活を作り込んでいく。そうした作業の巧さを日本の小売業者たちは実地で身につけている。この資質はそれだけで資源、財産と呼べるのではないか。私がコクピットに関わって学んだことを端的にいえば、そうなる。
需要の創造はメーカーや製品の開発に当たる人たちだけがなし得るものではない。むしろ、彼らがそれを得手とはしていないことはすでに述べた。
製品を売る人と買う人が知恵を出し合ったとき、需要の創造は成就する。この奇跡をシステムとしてうまくまとめたのがユニクロを配下に置く持株会社・ファーストリテイリングだろう。
ユニクロの製品を着ると、どんな楽しいことがあるのか。それを知っているのはお客さんだ。インターネットを介してユニクロはお客さんと意思疎通を図り、大々的に需要の創造を行ってきた。
新しい価値の提案を絶え間なく続けていく。そのための仕組みはすでにできている。成功は約束されたようなものだ。
私が現場で出会った小売店の店主たちには共通する特徴がいくつかあった。強い思いを持ってお客さんに接している。生活者を相手に「こんな楽しいことが起きるんだよ」と店を通じて完結した形で訴える。
誤解を恐れずにいえば、彼らは決して学のある人たちではない。だが、それがどうだというのか。いずれも個性派で人間としての魅力にあふれた人物ばかりだ。人間力に秀でた店主たちから私は有形無形の影響を受けた。
日本の受験教育の弊害に思いを致さずにはいられない。成績が優秀な者ほど、ものを生産する側に立つよう仕向けられてはいないか。理系神話、製造業信仰をいつまで続けるつもりだろう。
日本人特有の創造性は小売業の現場に根付いている。学歴とは関係のない位相で日本人が成功できる素地はある。もともと「語り」が好きな特性を生かさない手はない。ものをものとして売る限りは価格競争にどうしても陥る。規模の利点を生かし、量販店やディスカウントストアのような商いに活路を見出す方法を否定するつもりはない。だが、売り場を倉庫化するだけが生きる道でもないだろう。むしろ、売り場をアミューズメントパークにしてはどうか。
その延長線上に内需の拡大も見えてくる。小売業は日本の希望の一つだ。潜在的な力はある。何も難しい施策は必要ない。一言、「自由にやってごらん」と言ってやればいい。
グローバルに戦えるだけの地力をいかんなく発揮させる。現行の制度はそれを抑制する枷にしかなっていない。発展を阻害している。 「自分で売る」前提に立てば、開発者が生み出すプロダクツは確実に変わっていく。ユニクロのような「製造販売業」の強みはそこにある。優れた製造販売系の企業はいずれも生活者との距離が近い。小売業に優秀な人材が集まる。そんな経路を国内に作れないだろうか。小売の分野でとてつもない起業家、創業者が生まれる。そんな国へと生まれ変われれば、国力は自然と後からついてくるだろう。
Image: 狩野永徳 上杉本洛中洛外図屏風(左隻)