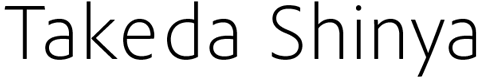広告代理店に勤め、販売促進を生業としていた頃の話だ。ある食品メーカーに呼ばれた。
「せっかく良いものを作っているのに、一向に売れない。販売促進のプロに売れる方法をうかがえないでしょうか」
その会社ではカップラーメンの新商品を開発し、売り出したところだった。
当時、販売促進の分野は「暗黒大陸」と呼ばれていた。ものづくりそのものには過剰なまでに関心を払うのに対し、どう売るかにはさほど興味を抱かない。販売への戦略などなきに等しい状態だった。
「良い製品を作り、問屋に卸す。そうすれば、あとは自然に売れていく」
メーカーの幹部クラスでも真面目にそう考えている人は少なくなかった。彼らの目で見れば、販売促進は確かに暗黒大陸そのものだったに違いない。
メーカーの開発部門には有名大学の理数系学部を卒業した受験秀才がひしめき合っていた。一方、販売促進のプロフェッショナルといえば、氏素性も定かではない集団に過ぎない。私もその一員だった。
どんなにいい商品でも販売店に仕入れてもらい、店頭に並ばない限りはお客さんの目に触れる機会はない。ましてや売れることなど決してあり得ないだろう。
やや専門的な用語を使わせてもらえば、流通チャネルの構築である。メーカーからお客さんまで、効果的かつ効率的な流通経路を経て商品を届けられるか。ものを売るためには物流をまず考えなければならない。
問屋に卸したはいいが、店頭に商品がない。そんなことはざらにある。とにかく確実に問屋に卸し、品切れにさえ気をつけていれば、自動的に商品は売れていく。そんな簡単な話ではないのだ。
流通とは生産者が生産した商品やサービスを販売者(卸売業者や小売業者)を経て消費者に提供するまでの流れのこと。大きくは「物流」と「商流」に分けられる。
物流とは物的流通の略語。商品が生産者から消費者へ提供される際のものの流れを指す。
商流とは商的流通の略語。商品が生産者から消費者へ提供される際の「所有権」の流れのことを言う。
私がここで強調したいのは物流や商流ではなく、「情流」である。情流とは商品が生産者から消費者へ提供される際の情報の流れ。一口に情報といってもさまざまなものが含まれる。生産者や販売者の情報、商品の情報など、ありとあらゆる情報が流通を支えている。
理想をいえば、カップラーメンそのものを店頭にポンと置いて売れる。そんなデザインが完成されていなければならない。メーカー側は「画期的な製品」と勝手にうたうものだ。だが、お客さんにしてみれば、店頭にある商品がそれほど変わりばえしているとはなかなか思えない。
販売店も新製品といえば、ひとまず並べてはみる。だが、なかなか売れなければ、やがて取り扱いをやめてしまう。
メーカーが必死の思い出開発した製品が小売店の取り扱いの問題で消えてしまう。そんな例は枚挙にいとまがない。
どんな製品であれ、きちんと売るには少し説明を加えてやる必要がある。例えば、味だ。店頭にある製品がある条件を満たさないとおいしくならないことはよくある。だったら、それを買い手に伝えなければならない。
そんな条件が解決されただけで製品がヒットすることもある。格好の事例がビールだ。
アサヒビールが現在の看板商品であるスーパードライを出すはるか前のことだ。東京・大森にアサヒが工場を建てた。
当時、中学生だった私は大森に住んでいた。父親に連れられ、ときどきアサヒの工場に出かけた。
父はこう言った。「ここはつまみは大したことがないんだけどな。ビールはうまいんだ」
その言葉に偽りはなかった。もう時効だから言わせてもらうが、未成年の私もたびたび父のご相伴にあずかった。
確かに工場で飲むビールはうまい。中学生にしては図体が大きかったので、まず見とがめられることはなかった。
家での晩酌では父は徹底した「キリン党」だった。アサヒのビールを飲んでいるところなど見たことがない。だが、大森の工場には嬉々として足を運んだ。アサヒの大森工場ではキリン贔屓の父を魅了するビールが供されていた。だが、酒屋で売られているアサヒビールは決してうまいとはいえなかった。なぜだろう。ヒントは流通にあった。ビールの味を決めるのは鮮度だ。酒屋をはじめ小売店には「先入れ先出し」という慣習がある。仕入れた製品は古いものから売っていく。酒屋では古いビールから順に売っていく。工場から入荷したばかりのうまいビールはなかなか店頭には並ばないのだ。私は工場でビールを飲み、鮮度の秘密を身をもって学んだ。
アサヒビールもいつまでも手をこまねいていたわけではない。あるとき、経営陣の肝煎で営業担当者が一斉に店頭の状況を調査した。全てのビールについて製造年月日を確認。いったん店頭にあるものは買い取った。これは紛れもなく英断である。今でもそう断言できる。その上でアサヒビールは「フレッシュローテーション」を施行した。店頭には新鮮な製品しか置かない。ここから「アサヒのビールは一味違う」という評価が浸透していったのだ。この施策と時を同じくして新商品・スーパードライが市場に投入された。その後、アサヒビールが首位キリンのシェアを切り崩し、王座をつかみ取るきっかけとなった。
店頭にある製品の日付を確認し、取り替える。それだけのことが強力な販売促進策になり得る。アサヒの事例は何よりの証左だ。同様の施策を愚直に繰り返し、効果を上げているメーカーは他にもある。菓子メーカーのカルビーだ。同社の営業担当者の責務は「古い製品を店頭から一掃すること」にある。それだけに徹していると言っても過言ではない。鮮度にこだわり続ける。この一点でカルビーはポテトチップスをはじめとするスナック菓子の分野で今日までゆるぎない地位を確保してきた。
流通は売り上げを左右する大きな要素である。消費者に対し、製品の全てを説明できればいい。だが、メーカーから卸、小売店と流通の過程で伝言ゲームを続けていくうちに重要な要素が抜け落ちるのは珍しくない。製品が店頭にたどり着いたときには雲散霧消していることもある。
製品が思ったように売れない。その理由の最たるものはコミュニケーション不全である。流通段階で「伝えるべきこと」が欠けてしまうのだ。些細なことに思えるかもしれないが、店頭で製品をどこに置くかも大事な情報の一つ。小売店が鮮魚売り場の脇にワサビを置いているのをよく見かける。こうした工夫が売り上げを左右する。生産者の意図が小売の現場に必ずしも伝わらない。そんな例はごまんとある。
何も難しい話ではない。売り場の現状を見に行けばいい。メーカーにとって好ましい状態で売られているかどうかをチェックする。だが、開発者の多くはそうした努力をしないものだ。
流通経路のどこで齟齬が生じているのか。確認を怠らない企業は数えるほどでしかない。
反対に言えば、流通の過程を見て、どうすれば自分たちの意図が消費者に伝わるかを考えている企業はそれだけで優良である。この点で秀でているのが花王だ。流通経路を常に整備。メーカーでありながら営業担当者を活用し、自社の製品がどう売られているかを注視し、改善している。
繰り返しになるが、技術的に難しい話ではない。流通の各段階を確認し、改善すべき点に手を下す。それだけのことで売り上げは改善できる。だが、多くのメーカーはそこまで思いをいたさず、販促を「暗黒大陸」と見なしている。
販促の担当だった頃、依頼を受けると、私はまず店頭に足を運んだ。ひどい場合は店頭に製品がない。あるとしても、まずメーカーが置いてほしいと考えているところにはない例がほとんどだ。
なぜ、そうなるのか。端的に言えば、売れないからだ。そこで対症療法的にやたらとリベートをつける。きちんとした情報が伝わらないままにリベートだけつけても効果は上がらない。高コストに耐えられず、せっかくの製品が消えていく。開発者の血と汗の結晶が戦線に出ていく前にである。これほど残念なことがあるだろうか。
流通上のコミュニケーションギャップを拾い上げ、解消法を提案する。それだけで売り上げは変わる。現役時代、私はそうしてお金を取っていた。
販促とは泥臭い行為だ。問屋の営業担当者が何をしているか。同行して調査する。実際のところ、彼らは製品をいち早く現場に送ることしか考えていない。言葉を選ばすに言えば、営業担当者ではなく、高速販売人、配達屋に過ぎないのではないか。営業担当者の給与体系を見れば、よくわかる。1日に何軒得意先を回ったか。それだけが基準と言っていい。情報を伝えることは重視されていない。細やかな説明などしていれば、たちまち評価は落ちてしまうだろう。
家電メーカーの開発担当者を同伴し、量販店の店頭に行ったことがあった。彼の作った冷蔵庫はどこにあるか。実際に目にすると、仰天する。彼が思い入れを込めた部分が消費者には全くアピールされていないからだ。
製品が思うように売れないとき、メーカーの販売担当者は広告代理店を頼りがちだ。代理店にとって当時はテレビコマーシャルを売ることが最も都合が良かった。
確かにCMを打てば、売れた。全く知られていない製品が世に出るときはそれでいい。
だが、消費者のリテラシーもやがて高度化していく。単なる認知だけでは売り上げは変わらくなっていく。認知させ、興味をわかせ、理解を得て、確信を持たせ、ついには買わせる。確実に売るためには認知理解どの段階を踏む必要がある。
流通上のコミュニケーションギャップがある場合、いくら広告を打っても効果はない。それはそうだろう。店頭に商品がないのだから。
マーケターはマーケティングと売り上げとの因果関係には大きな関心を払っている。自分たちがどれだけ情報を出し、どれだけの効果が上がったか。その点はつぶさに見ているものだ。だが、流通の経過にまでは目を向けない。その結果、多くの製品が残念な状況にある。
流通上のコミュニケーションギャップを簡単に解決したのが製造小売業だった。この点は以前のコラムでも触れた通りだ。
タイヤのような商品は最も物流に頼って売られている。そこでブリヂストンは自社で小売店を組織した。その結果、意図した通りに商品が浸透していった。
とはいえ、自前の小売業を持てるメーカーは限られている。ブリヂストンの真似はそうそう簡単にはできない。
販売促進の周辺では何かといえば、データが飛び交う。だが、そのデータがなぜ出てくるのかまでは考えない。現場で手で触って確認する作業が不足している。パソコンのモニター上で電子カルテは見ても、目の前の患者には目を向けない。そんな医師のようなものだ。
大手コンサルティングファームの販売促進策はデータの分析が多くを占めている。現役時代、私もそんなペーパーを何度か見た。そのたびに「これじゃ売れない」と思ったものだ。
データは常に結果でしかない。それらを分析しても、原因を作っている部分には光を当てられない。日本の現場主義、現物主義は決して古臭い発想ではないのだ。
マーケティングはかっこいい仕事。最近ではそう誤解されている節がある。空調の効いたオフィスでパソコンの前に座り、グラフを解析するだけ。それで解決策が生まれれば、こんな楽なことはない。
現場ではもっと泥臭い理屈でものが売れていく。例えば、洗剤だ。雨が降ると、大箱の製品は売れない。持って帰るのに難儀だからだ。
右利きが多数を占める以上、売り場の右手に置かれる商品はそれだけで優位にある。当たり前といえば、当たり前。ばかばかしいと思えるような要因で売り上げが左右される。そんな例は少なくない。
今、世の中に流通している商品の多くは嗜好品である。必需品ではない。人々はいりもしないものを買っているのだ。
嗜好品を買うとき、人間の選択は往々にして合理性を欠いていることが多い。商品が合理性だけで売れていると考えるのは早計だ。経済学の原理は人間は合理的判断に基づいて行動すると規定している。だが、現実にはそうでないことも多い。販売促進のプロなら皆知っている。これは経済学の根本的な弱点だろう。
いくら学問に通じたとしても、商売はできない。本来不合理な人間の購買行動。それをいかに主人公の身になって、生活の中で現実的な楽しさを付与していくか。需要の創造というマーケティングの新たなフェーズがここにある。
GDPの多くを占める消費。だが、日本人が持つ資質がうまく生かされず、伸び切れていないようだ。もどかしさを感じる。
現場で学んだ私の実感を若い方にもぜひ共有してほしい。簡単なことだ。
「お前、行ってみろよ」
それだけである。